Django:「今回はピアノの話。」
Murphy:「ジャズピアノは、オスカー・ピーターソンとかビル・エバンスなどは何枚かアルバムを持っているんだけど。そのあたりの話題?」
D:「もっと新しい人。現役だよ。」
M:「若手ピアニスト?」
D:「そう。といってももう40を過ぎているけど。マーカス・ロバーツ、って知ってる?」
M:「知らないなあ。黒人のピアニスト?」
D:「そのとおり。マーカスは、1963年生まれ。フロリダ出身の盲目のピアニスト。1985年にウイントン・マルサリスのバンドに抜てきされた。デビュー当時ニューヨーク・タイムズは、20年来の逸材だと絶賛した。」
M:「へえー、そんな大物なの。マルサリスのバンドに入ったぐらいだからすごいね。」
D:「彼のリーダーアルバムを聴いて、”スタインウェイは、マーカスのためにあったのか!”と思ったね。」
M:「スタインウェイって、あのピアノメーカーのこと? それ、どういうこと?」
D:「ピアノは、自在に音色を変えられない。弦楽器のようにビブラートもかけられない。サックスのように細かな息づかいまで表現できない。本来自分の感情をダイレクトに伝えるには、ピアノは他の楽器に比べ、かなりの制約がある。ところが、優れたピアニストの手にかかると、こういった先入観が見事にくつがえされる。ひとたびスタインウェイがマーカスの手にわたると、ピアノが目覚めたかのように生き生きと反応しだし、雄弁に語りかける。息づかいや細かな感情までも伝わってくる。ピアノってここまで豊かに感情を表現できるのかと、驚いてしまう。」
M:「Djangoくん、マーカス・ロバーツ絶賛しているね。」
D:「マーカスをはじめて聴いたときの衝撃は今でも鮮明に覚えている。彼のピアノは、ラグタイム、ブルース、ニューオリンズスタイルにルーツを持ち伝統を継承しながらも、彼独自の新しいスタイルを打ち出している。左手の動きがきわめてユニーク。右手の歌うようなメロディーライン、語りかけるようなフレーズ、そして本物のブルースが飛び出してくる。まさにジャズなんだ。しかも、彼のピアノは、ジャズという狭い枠を飛び越え、クラシックのピアニストを含めてもこのレベルの人を見つけるのが困難なほど、音楽的にきわめて高度なレベルに到達している。」
M:「へえー、そんなにすごいのか。」
D:「ボクか感じたことは、彼の演奏はすべてアドリブにもかかわらず、クラシックの作曲家が一音たりとも妥協を許さず綴った楽譜と同じくらいのレベルに達していると思ったこと。それでいて曲の展開がまったく予測できないほど、スリリングで斬新。言葉がものすごく豊富だね。全くムダがない。かといって、堅苦しくもなく、きわめてリラックスした演奏。こちらが真剣に耳を澄ますほど、語りかけてくる音楽だ。Murphyくん、彼のアルバム、是非ヘッドフォンで聴くことだな。そうすると、初めて彼の気持ちが伝わってくるよ。」
M:「彼の演奏に集中して聴くということか。わかった。ヘッドフォンだと集中できるしね。」
D:「それと、ジャズファンだけでなく、広くクラシックファンにも、特にピアノを演奏している人にも教えてあげたいね。」
M:「アルバムは、どのくらいあるの?」
D:「おそらく30枚近くにのぼるかな。スコット・ジョップリン、ジェリー・ロール・モートン、ガーシュイン、コール・ポーター、セロニアス・モンク、デューク・エリントン、ナット・キング・コールなど、まさにジャズの歴史といえる多くの巨人たちの様々なスタイルと曲を採り上げている。重要なのは、マーカスのアルバムが、単にモダンジャズの狭い枠にとどまらずに、ブルース、ラグタイムからニューオリンズ、スイングなどを含む、実に広い過去のジャズ遺産を継承していること。今回は、数あるアルバムのなかで、比較的新しい2001年にリリースされた、”コール・アフター・ミッドナイト(Cole After Midnight)”を選んでおこう。マーカスだけは、1枚だけに絞り込むことは不可能だけど。このアルバムは、ピアノトリオで、”ナット・キング・コール”(下写真)の名曲(“コール・ポーター”の作曲を含む)をフィーチャーしたもの。
![]()
その中の15曲目の”コール・ポーター”作曲の”イッツ・オールライト・ウイズ・ミー(It’s All Right With Me)”は、きっとMurphyくんも聞き覚えのある軽快な曲だよ。それから、イントロとエンディングの”Answer Me, My Love”は、実に深々とした演奏。この曲は知らずに聴くとクラシックの演奏家と思うかもしれない。」
M:「”イッツ・オールライト・ウイズ・ミー”、曲名は聞いたことあるな。確かオスカー・ピーターソンがよく演奏していなかった?」
D:「そのとおり、1953年のミュージカル”カン・カン”のナンバー。エラ・フィッツジェラルドの得意曲でもあるし、クリス・コナーも歌っている。それこそみんな知っている曲だね。」
◇◇◇
Cole After Midnight / Marcus Roberts Trio, Sony Music 2001
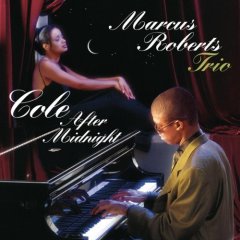 Cole After Midnight
Cole After Midnight
月: 2007年3月
第33回 不滅のジャズ名曲-その33-聖者の行進(When The Saints Go Marching In)
Django:「Murphyくん、ニューオリンズ・ジャズで知っている曲は?」
Murphy:「ニューオリンズ・ジャズってディキシーランド・ジャズのことだろ?」
D:「そう。ディキシーランドというのは、アメリカ南部の州を指す通称だからね。」
M:「それなら知っているよ。だれでも知っている曲で、”聖者の行進”。」
D:「今回は、その曲を採り上げようと思うんだ。」
M:「へえー、こんなポピュラーな曲を? あまりにも知られすぎていて、面白くなさそうだけど。どうしてこんなものを採り上げるの?」
![]()
D:「おいおい、”聖者の行進”をバカにするなよ。Murphyくんは本場の演奏を聴いたことある?」
M:「ないね。アマチュアバンドぐらいかな。」
D:「本場のニュー・オリンズで、演奏しているグループのものを聴けば、認識新たにすると思うよ。」
M:「本場って、どんなバンド?」
D:「プレザベーション・ホール・ジャズ・バンド(Preservation Hall Jazz Band)というグループ。このバンドは、ニューオリンズ市内にあるプレザベーション・ホールの専属バンド。このホールは、地元のジャズメンたちによって1950年代から毎夜ライブ演奏が行われていた場所で、今やニューオリンズ・ジャズの遺産を継承したシンボルとして位置づけられるジャズのメッカなんだ。建物は古いけどね、それだけにリアリティがあるんだ。新築の立派なホールでは決して味わえない、手作りのアットホームな雰囲気がある。」
M:「このあいだのニューオリンズを襲ったハリケーンで問題なかったの、このホールは。」
D:「フレンチクォーター付近にあるんだけど、やはり半年間は閉鎖された。その間このバンドは、全米ツアーに出かけ演奏していたらしい。ところで、そのバンドの92年のライブアルバムがあるんだけど。」
M:「そのバンドってどんな編成なの?」
D:「トランペットまたはコルネット、クラリネット、トロンボーン、ピアノ、ベース、ドラムス、バンジョーの7〜8名の編成。実はこのアルバムに吹き込んだ、クラリネット奏者のウイリー・ジェイムス・ハンフリー(Willie James Humphrey)は、1900年12月生まれ。1994年になくなっている。このアルバムの録音年月日は、アルバムに書かれていないが、おそらく80〜90歳、あるいは90歳を過ぎてからの録音かも。弟の、パーシー・ハンフリー(Percy Humphrey)が、トランペットを担当している。」
M:「90歳過ぎても現役で演奏していたのか? 驚いたね。」
D:「ウィリーは93歳で亡くなるまでこのホールで演奏していた。すごいだろう。現役最長老のハンフリー兄弟のバンドの演奏は、これが本場のジャズだというべき、実に生き生きした演奏で、本当に素晴らしいよ。ウィリーの祖父はコルネット奏者で音楽教師。父親がクラリネット奏者のWillie Humphrey Sr.で、同じニュー・オリンズ出身のマルサリス一家のように、家族全員音楽一家。ウィリーは、1920年頃キング・オリバーと共演したほどの実力の持ち主だ。1960年代から弟のパーシーとともにPreservation Hallで演奏している。それでね、Murphyくん、このアルバムには、ニューオリンズ・ジャズのエキスのような曲が詰まっていて、最後に”聖者の行進”で締めくくっているんだ。この曲の演奏時間はなんと、8分09秒の長時間にわたっている。」
M:「ヴォーカルは入ってないの?」
D:「弟のパーシーが歌っている。これがまた味のある歌だね。まさにヴィンテージものだね。それにしても、兄弟ともに70年以上演奏してきたんだから、そのリアリティはすごい。それとウィリーの演奏には、他には真似のできない独特のリズム感がある。微妙に遅れ気味のなかに絶妙なスイング感が宿っている。とにかく、バンドがものすごくスイングしている。ジャズなんだよ。まさにジャズ。ジャズの香り、楽しさ、面白さがダイレクトに伝わってくる。」
M:「ところで、このバンド、バンジョーが入っているんだね。」
D:「そう。聴いてみれば、どうしてギターでなくバンジョーなのかきっとわかるよ。」
◇◇◇
※本CDはリリース後15年経過しており、やや入手困難かと思われます。でも、他に代え難い貴重な演奏ですので、もし発見されましたら、ぜひご購入をおすすめします。
Preservation Hall Jazz Band Live / 1992 Sony Music SK48189

第32回 不滅のジャズ名曲-その32-チェロキー(Cherokee)
Django:「今回は、燻銀のトランペッター、”ジョー・ワイルダー(Joe Wilder)”を採り上げる。」
Murphy:「聞いたことないね。」
D:「ジョー・ワイルダーは、マイルスやクリフォード・ブラウン、ケニー・ドーハム、アート・ファーマーなどのように、知名度があるわけではない。しかし、その実力は第一級で、何よりトーンの美しさは特筆すべきものがあるんだ。歌うようなメロディーライン、シンプルな中にもスインギーなアドリブは、他に代え難い魅力を持っている。」
M:「そうか、ほとんど知られていないのか。アルバムの数は?」
D:「あまり録音していないんだ。」
M:「いつ頃の人?」
D:「ジョーは、1922年2月22日生まれ。マイルスが1926年だから、4歳年上だね。」
M:「そうすると同世代になるのか。どこの人?」
D:「ペンシルバニア州コルウィンで生まれ、フィラデルフィアで育った。」
M:「フィラデルフィア出身のジャズマンも多いんだね。その後は?」

![]()
D:「父親がバンドリーダーで、12歳のときにその父親からトランペットを学んだ。その後、音楽学校に入学し、卒業後レス・ハイト楽団に入団。そこで、ディジー・ガレスピーと共演した。42年からは、あの有名なライオネル・ハンプトン楽団の所属する。その後、いくつかの楽団を歴任し、50年代からブロードウエイの劇場オーケストラに所属。54年には、カウント・ベイシー楽団の欧州ツアーに参加。このころから多くのジャズメンと交流する。当時、彼の実力は相当なレベルに達していたようだ。」
M:「ジャズのプレイヤーって、ほとんど最初は、楽団に所属する人が多いんだね。」
D:「その当時はね。そこで鍛えられるんだ。62年にはベニー・グッドマン自らの要請でソ連へのツアーにも参加。以降は、フリーランサーとしての仕事と、レコーディング、
![]()
ニューヨーク市のコンサートオーケストラのソリストを初めとするオーケストラでの活動が中心だった。」
M:「ということは、比較的地味で堅実な生活だったのか。」
D:「そうだな。当時のアメリカには、ジョーのように本当の玄人好みのミュージシャンが多数存在していた。そのあたりが、ジャズの底辺をしっかり支え、根付かせていたと思うんだ。オーケストラ活動の合間に、ひとたびジャムセッションをすれば、有名ジャズメンと互角、あるいはそれ以上のパフォーマンスを披露した。いたずらにスター・プレーヤーを目指さず、地道に音楽を追究しながら、自分の音楽生活を楽しんでいたと思うんだ。決して、有名ジャズメンばかりが、ジャズを支えたのではないっていうこと。目立たない隠れたなかに一流のミュージシャンが潜んでいる。このことをしっかり認識しておかなければならないと思う。」
M:「そうだなあ。ともすればスタープレーヤーばかりに目がいくものね。マイルスを聴いてそれだけでジャズがわかったことにはならないということか。」
D:「Murphyくんの言うとおりだよ。ジョーのようなほんとうに音楽を知っていてうまいミュージシャンの演奏を聴くとわかるよ。実は、ジョーは、クラシックのアルバムも残しているんだ。ハイドンやサンサーンス、ルロイ・アンダーソンなんかの曲を録音している。今でこそ、ウイントン・マルサリスのようにジャズとクラシックの両方を演奏するミュージシャンもいるけど、当時はあまり前例がなかったと思うね。ところで、”チェロキー”っていう曲知ってる?」
M:「ああ、知ってるよ。確かクリフォード・ブラウンも録音しているね。」
D:「そのとおり。ガレスピーもよく演奏したスタンダード曲だ。ジョーも50年代にSAVOYに吹き込んでいる。「ワイルダーン・ワイルダー」というアルバムで、1曲目に演奏している。この”チェロキー”いいよ。普通はこの曲、アップテンポなんだけど、ミディアムテンポで原曲のメロディーラインを大切に歌い上げている。ジョーのスインギーで流麗なアドリブも素晴らしく冴えわたっている。音色も抜群。それと、リズム陣がまたいい。あのハンク・ジョーンズがピアノを担当している。ハンクは、シンプルで控えめながらいつも音楽が深い。ジョン・ルイスとハンク・ジョーンズは本当に音楽とは何か、ということを実に良く知っているね。このアルバムを聴いていると、ああ、ジャズを聴いていて本当によかったってつくづく思うね。」
M:「そうすると、”ジャンゴ効果”も高そうだね。」
D:「そりゃもう。”ジャンゴ効果”100%を超えてしまっているよ。」
※本文中のジョー・ワイルダーの履歴に関しては、「ワイルダーン・ワイルダー(キングレコード)」LPレコード付録の大和明氏のライナーノート(1989)を参考にした。
◇◇◇
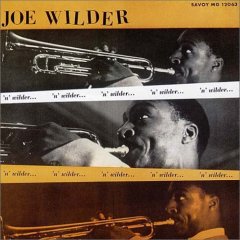 ワイルダーン・ワイルダー/ジョー・ワイルダー SAVOYレーベル
ワイルダーン・ワイルダー/ジョー・ワイルダー SAVOYレーベル
第31回 不滅のジャズ名曲-その31-ウエスト・エンド・ブルース(West End Blues)
Murphy:「Djangoくんの最も好きなJazzミュージシャンは誰なの?」
Django:「いきなり質問?」
M:「Djangoくんは、けっこう幅広くJazzのこと知っているから、一番好きな人は誰なのかなあって、思ってたんだ。おそらく、ジャンゴじゃないかって予想しているんだけど。」
D:「もちろん、ジャンゴは、大好きだよ。名前からしてDjangoだもの。」
M:「と、いうことは、一番じゃないのかな?」
D:「一人だけ選ぶなんて無理だよ。自分の好みもその時々によって変わるだろうし。」
M:「いや、きっと、Djangoくんは、この人だと思っているけど、言わないだけだろう?」
D:「そんなことない。まあ、どうしてもMurphyくんが、一人だけあげろと言うんなら候補はあるけど。でも、先に言っておくけど、他にも自分の気に入ったアーティストは、本当に多いんだから。」
M:「それはわかっているよ、早く言えよ?」
D:「それなら、言います。ルイ・アームストロングだね。」
M:「へえー、意外だったな。Djangoくん、あれだけモダンジャズが詳しいのに。」
D:「ルイ・アームストロングは、まさに”キング・オブ・ジャズだね。LPの頃から数えても自分の持っているアルバムのなかでルイが一番多いかな。」
M:「で、どこが魅力なの?」
D:「あのノリのよさ。太い音。独特の歌声、巧みな間と即興のスリル、音楽をやっているのがこんなに楽しいっていう実感。全身ジャズだね。明るくホットなジャズ。理屈抜きで楽しめる。今でもどこかなつかしい香りがする。挽きたてのコーヒーの香りかな。そして、これが一番決定的なんだけど、ブルース精神だ。ブルースだよ。彼ほどうまいブルースが演奏できる人はそうはいないよ。抜群のスイング力で、”ジャンゴ効果”の最も高い音楽だね。」
M:「そうか、なるほどなあ。ジャズって結局はそれなんだね。ところで、サッチモのことって、これまであまり知らなかったんだけど、いつ頃どこで生まれた人なの?」
D:「で、少し説明を。ルイは、1900年7月4日にニューオリンズで生まれた。当時、ニューオリンズの街にはラグタイムやブルースが流れていた。ルイは貧しかったので小学校にも行けず、ストリートキッズだった。1913年の正月に、ルイは爆発する。クリスマスや正月っていうのは、貧乏人は不幸が身にしみる。ついに、ピストルを持って打ちまくった。幸いけが人はなかった。この事件で、ルイは少年院に入る。」
M:「へえ、13歳で。」
D:「ところがこれがラッキーだった。少年院で、楽器を手にする。最初は、タンバリン。1年後についに念願のコルネットのポジションを手に入れる。その後は、水を得た魚のように毎日練習に明け暮れた。ブラスバンドではなんと言ってもコルネットが花形だから、よほどうれしかったんだろう。2年後、退院。しかし、コルネットの持ち出しは出来なかった。家に帰り、毎日毎日コルネットのことばかり考える。欲しくて仕方がない。そこで、コルネットを買うために、石炭の運び屋になる。夜になれば、音楽を聴きたくてダンスホールの近くをうろつくことが日課となる。」
M:「なるほどそれで音楽を覚えていったのか。」
D:「当時のニューオリンズは音楽を覚えるには最高の環境だよ。その後ルイは、あるコーヒーショップでコルネット吹きの仕事を見つける。コルネットが貸し与えられた。ところが、しばらく吹いてなかったので唇が弱っており残念ながら
![]()
思うように吹けなかった。それで楽器がだめなら歌でいこうと、ブルースを歌ったところこれが受けた。歌を歌いながら得た収入でついにコルネットを購入、そして練習に励んだ。」
M:「ここからだね。ルイのスタートは。」
D:「唇も回復し、歌とコルネットの両方で演奏するようになる。ルイは、曲のテーマをたくみに変奏する能力に長けていた。即興演奏を強調するようになる。次第にルイの名前は知れ渡る。音の大きさでは絶対に負けなかった。歌にも磨きがかかる。いよいよルイは一芸の枠を超えていく。その評判は、ニューオリンズ一帯に広まる。そして、ある日トランペットの王様、キング・オリバーがシカゴから噂を聞きつけて、ルイに会いにやってくる。」
M:「運命の出会いだね。」
D:「第一次世界大戦に入り、出兵のためニューオリンズは寂れていく。1922年キング・オリバーから、シカゴへの誘いの手紙が届く。かくしてルイは、ジャズの街大都会シカゴへ旅立つ。そしてついに、オリバー楽団に入る。身近にキングの音楽から学んだことは、計り知れないものがあった。田舎から出てきたルイは、純朴なるが故みんなから愛される。1925年オリバー楽団のピアノのリル・ハーデンとめでたく結婚。彼女から、楽譜の読み方、記譜法、編曲法にいたるまで連日音楽理論の特訓を受ける。そして、この年、オリバー楽団から独立し、ニューヨークの当時ビッグバンドの最高峰といわれたフレッチャー・ヘンダーソン楽団に入団。ちなみに当時、この楽団で編曲の仕事をしていたのが、後のスイング・ジャズブームの仕掛人、ベニー・グッドマンだった。ルイは、その年の末には、ふたたびシカゴに戻る。そしてついに、念願の自己バンドを結成し、決定的な評価を受ける。オーケーレコードからレコーディングの誘いを受け、数々の名演奏を録音する。この間の演奏がいわゆるルイの前期黄金時代である。」
M:「Djangoくん、ルイのことよくわかったよ。」
D:「その前期黄金時代の1925-30年までの演奏は、「The Hot Fives & Sevens」に収録されている。LP時代は、CBS、CD時代はソニーレーベルなんだけど、もうこの時代のルイの演奏は、本当に素晴らしいよ。あと、戦後の50年代もふたたびコンボで演奏をおこない、数々の名アルバムを残している。これが後期黄金時代。ボクはLP時代からの大ファンで、LPを持っていながら、改めてCDを購入している。CDのソニー盤について、特に戦前のオーケーレーベル時代のものは、音質の面で若干の不満を持っていたんだけど、1999年にイギリスのJSPレコードが、復刻Boxセットをリリースした。このインパクトは大きかったね。いまではこのJSP盤があるから、LPをかけなくてもいいようになった。Murphyくんには、ぜひ、このJSP盤をすすめるよ。」
M:「そうか、わかった。ところで、Djangoくん、おすすめの曲は?」
D:「コンボの演奏は全部いいんだけど。やはり、ブルースだね。ウエスト・エンド・ブルース(West End Blues)、最高だね。日本の世界に誇るジャズピアニストの秋吉敏子さんも、初めて買ったLPが、ルイのウエスト・エンド・ブルースだったそうだよ。」
◇◇◇
Louis Armstrong 1925-30 The Hot Fives & Sevens [Box set]
 The Hot Fives & Sevens
The Hot Fives & Sevens
第30回 不滅のジャズ名曲-その30-ビリーズ・バウンス(Billie’s Bounce)
Murphy:『Djangoくん、ギターのことで聞きたいんだけど。ジャズ・ギターってどうしたら弾けるようになるの?」
Django:「練習を積むことだね。」
M:「それは、わかっているんだけど。ギターに限らずジャズの人って、アドリブが自在にできるよね。どうしたらできるのか不思議なんだ。」
D:「Murphyくんもジャズをやりたいの?」
M:「いや、そういうわけではないんだけど。いつもアコースティック・ギターを弾いていて、ほとんど譜面どおりなんだ。たまに、アドリブらしきものをやっても、ペンタトニックやダイアトニック・スケールで作るフレージングは、何とか出来るんだけど、ジャズにはならないし、やっぱりどう考えても不思議なんだ。ジャズが弾けるということが。それに、ジャズっていろんなスタイルがあるだろう。スイング・ビバップ・ハードバップ・クール・ファンキー・モードとか、いっぱいあるから、ますますわからなくなってくるんだ。」
D:「Murphyくん、一応ジャズの歴史、知っているんだね。いつのまに、勉強したの?」
M:「いや、ちょっと本を読んだだけなんだ。そしたら、1910〜20年代までは、ニューオリンズ・ジャズが全盛で、30年代にはビッグバンド中心のスイング時代に入った。その後、40年代からビバップ・ムーブメントが起こり、いわゆるモダン・ジャズになった。50年代半ばからハードバップ、そしてファンキーへと続く…、確かそういうストーリーだったような気がするけど。」
D:「確かにそのとおりだけど。」
M:「それで、Djangoくんに聞きたくなったんだ。そういうスイングとかビバップとかハードバップっていうのは、全然違うの? Djangoくんは、どのあたりのスタイルが得意なの?」
D:「それほど明確には区別してないけど。基本はそんなに変わらないし…」
M:「それ、どういうこと?」
D:「確かにスイングからビバップへは、大きく表現が変わったけどね。その後の、ハードバップ以降っていうのは、基本的にはビバップのフレーズの派生型だね。」
M:「その程度なの?」
D:「確かにジャズ史的にみれば、そのようにムーブメントが発展していくのかもしれないけど。前の時代の音楽と次の時代の音楽が、それほど一気に明確に変化しているとは思わないなあ。それと、どちらかと言えば、「発展」とは言いたくないね。前の時代でもいいものがたくさんあるし。新しいスタイルが出てきて古いスタイルがなくなるわけではない。次の新しい時代だといわれても、依然として前の時代のスタイルも脈々と根付いていたと思うね。新しいっていっても、ちょっとスタイルが変わる程度かな。」
M:「なるほどね。確かにビバップとハードバップの違いって、はっきり区別できないよね。」
D:「そのとおり。基本的には、今の時代の演奏もやっぱりビバップ・フレーズが基本だしね。ソニー・ロリンズもクリフォード・ブラウンも、パーカーやガレスピーなどと、フレーズをつくっていく理屈やハーモニーに関しては、そんなに違いはない。その人の個性の方が大きいよ。だた、ひとつ言えることは、40年代に、チャーリー・パーカーを中心に、 ガレスピーなどのグループが、飛躍的にアドリブの可能性を広げたということ。ジャズのアドリブは、ハーモニーを基本に展開しているんだけど、特にパーカーのフレージングが画期的だったということだね。パーカー以降は、様々なアーティストが登場するが、表現手法は異なっても、基本はみんなビバップ的な発想でアドリブを展開しているんだ。」
ガレスピーなどのグループが、飛躍的にアドリブの可能性を広げたということ。ジャズのアドリブは、ハーモニーを基本に展開しているんだけど、特にパーカーのフレージングが画期的だったということだね。パーカー以降は、様々なアーティストが登場するが、表現手法は異なっても、基本はみんなビバップ的な発想でアドリブを展開しているんだ。」
M:「そういうことか。みんなジャズのアドリブは、コード進行に基づき展開しているってことだね。」
D:「そう。一部の例外はあるけど、基本的にはそのとおりだ。」

ー 休 憩 ー
M:「また素人考えなんだけど、アドリブってアルペジオみたいなもの?」
D:「まあ、そういうことだね。フレーズでハーモニーを表現していくんだから、バーチカルに展開していくんだ。その上で、ビバップ・フレーズは、代理コードを使って、別のコードに置き換えたりする。それと、テンション・ノートも付けていく。」
M:「だんだんわからなくなってきたよ。今回はこの程度でいいよ。それにしても、パーカーの存在はすごいんだね。」
D:「ところで、Murphyくんは、パーカーの演奏聴いたことある?」
M:「もちろんあるんだけど。何回かは、でも...」
D:「でも?」
M:「なんだかむずかしそうだよ。」
D:「そうか。どんなアルバム聴いたの?」
M:「あまり古い録音もいやだし、確か50年代のものだったと思う。」
D:「わかった。Murphyくん、パーカーはやっぱり40年代の演奏をまず聴いた方がいいよ。SavoyやDialに吹き込んだもの。演奏は1曲3分前後だから。何回か聴いていくうちに、パーカーのフレーズに親しみを覚えるよ。」
M:「そのSavoyかDialか、どちらを先に聴けばいいの?」
D:「両方だよ。Murphyくん、1940年から48年までのパーカー絶頂期の演奏を1つにまとめた、いいアルバムがあるよ。セットなんだけどボクはこれをすすめるね。以前ジャンゴの時に採り上げたイギリスのJSP Recordsがパーカーの決定版ともいえる、ほんとにいい復刻盤を出してくれた。さすがJSPだけあって、音質は向上しているし、しかも低価格。5枚組で3000円切れるよ。パーソネル、録音年月日などのデータもしっかり記述されているし、JSPのこのセットは、いずれ在庫が切れて品薄になれば値段も上がるだろうね。」
M:「パーカーの代表曲ってなに?」
D:「いろいろあるけど。例えば、ビリーズ・バウンス(Billie’s Bounce)。Murphyくんもこの曲練習してみたら。」
◇◇◇
A Charlie Parker: A Studio Chronicle 1940-1948 イギリスJSP Records 5枚組Boxセット

第29回 不滅のジャズ名曲-その29-バット・ノット・フォー・ミー(But Not For Me)
Murphy:「前回のビール・バーのデザイナーから、また問い合わせがあったんだけど。ジャンゴについては、文句なしということで非常に気に入っている。それで、時たまジャズ・ヴォーカルを流したいんだけど、誰がいいかDjangoくんにぜひ聞いてほしいということなんだ。ヴォーカルも、どこにでも流れているようなものではなく、こだわりを持って選曲するほうがいいだろうって。」
Django:「確かにその通りだね。ヘレンメリルのYou’d Be So Nice To Come Home Toなんかだと、最近どこの店でも流れているしね。”一応ジャズをかけています”っていう程度で、体裁だけととのえてそれ以上のお店のポリシーが感じられない。店主のこだわりというか。だから今度のその店は、新しいビール・バーということで、せっかくジャンゴを選んだんだから、ヴォーカルもそれに見合うだけのものが必要だ。」
M:「ボクもそう思う。最近やたらジャズをかける店が多くなって、有線か何か知らないけど、流れているものは、居酒屋も、寿司屋も、カフェも、何かおきまりの定食のような感じだから。Djangoくんの言うようにもっとこだわり持て!って、言いたくなるね。まあ、一般はそれでいいかもしれないけど、今度のお店は、こだわりの店にしようということだからね。何かいいアイデアある?」
D:「そうだな。ジャンゴが、戦前の古い録音だから、ヴォーカルもそのように…」
M:「そうすると、古い時代のもの、っていうこと?」
D:「そのとおり。」
M:「黒人のシンガー? それとも白人? 確かそのデザイナーが言ってたけど、黒人女性のヴォーカルは、ちょっとくせが強くて一般には聴きづらいのではないかって。だから白人女性シンガーあたりでどうか、と言っていたよ。」
D:「白人女性シンガーね。別のコンセプトの店なら合うけど。ここは黒人女性シンガーでいこう!」
M:「でも、大丈夫? せっかくジャンゴを選んだのに、ムードを壊さない?」
D:「そんなことないよ。黒人シンガーでもいろんなタイプがいるから。まず、選ぶにあたって、相当実力のある女性シンガーを選ぶべきだな。中途半端な、素人に毛が生えたようなシンガーはだめ。その上で、聴いている方は、その歌手が黒人か白人か、区別がつかないような人?」
M:「そんなジャズ・シンガーっているの?」
D:「いるよ。それが、エラ・フィッツジェラルドだよ。歌のうまさは天才的。そのうえ、バラードは実にしっとりと歌い、暖かみがあり情感が伝わってくる。サラ・ボーンなんかは、すごく黒人ぽい歌い方をするんだけど、彼女は、歌い方に変なくせもないし。クラシック好きの人でも、おそらく納得し、脱帽だろうな。アップテンポの曲も、思いっきりスイングして、ひとたび調子にのれば、アドリブで自由自在にスキャットができる。変幻自在だね。」
M:「へえ、そうなの。」
D:「それで、これからがポイントなんだけど、彼女は、1917年4月にヴァージニア州で生まれている。一般に市場に出回っている アルバムは、50年代の半ば以降で、年齢でいえば、40歳過ぎてからの吹き込みが圧倒的に多いんだ。」
M:「そりゃそうだね、1960年の録音なら43歳か、70年なら50歳以上だ。」
D:「もちろん、これほど歌のうまい彼女のことだから、50歳を過ぎても第一線でバリバリ活躍できたし、今でもその頃のアルバムも素敵だと思う。でも、彼女の若い頃の歌声は可憐で初々しくて本当に素晴らしいよ。もっと聴いてあげてもいいくらい。だから、今回は、エラを起用して、あまり一般には聴かれていない50年代までのアルバムで統一すればいい。30代の頃までの録音だね。そうすると、ジャンゴと時代的にも統一がとれるから。」
M:「なるほど、Djangoくん、うまいこと考えるね。」
D:「Murphyくんも、そのころのアルバムを一度聴いてみたら?」
M:「でも、その時代のアルバムって、簡単に手にはいるの?」
D:「最近はね、いい復刻盤が出てきたよ。それでね、ピアノのエリス・ラーキンスという歌伴の名人と2人で録音した曲があるんだ。そのなかで、おすすめは、バット・ノット・フォー・ミー(But Not For Me)という曲。このあいだ出てきたガーシュインの作曲。ジャズ・スタンダードとして大変人気のある曲で、これまでいろんなアーティストがこの曲を採り上げてきた。まさに名曲だね。例えば、歌では、ダイナ・ワシントン、クリス・コナー、リー・ワイリー、チェット・ベイカーなど。演奏では、マイルスがバグズ・グルーブというアルバムのなかで採り上げている。」
M:「ところで、そのバット・ノット・フォー・ミーの入っているアルバムは?」
D:「彼女も何度も録音しているけど、ここは、エリス・ラーキンスの歌伴で1950年に吹き込んだのを選ぼう。アルバム名は、「Ella Fitzgerald Vol.3 Oh! Lady Be Good」。彼女の1945年から52年までのレコーディング。レーベルは、イギリスのNAXOS JAZZ LEGENDS(直輸入盤)。NAXOSは、このところ大変いい復刻盤を次々と出している。デジタルリマスター技術により相当音質がよくなっている。このアルバム、全17曲中、8曲はピアノ1台による伴奏で、他はトリオ、オーケストラ伴奏。これ一枚で、彼女の多彩な歌い方が楽しめるんだ。」
M:「わかった、とりあえずそのアルバムをデザイナーに紹介するよ。」
D:「ところで、そのデザイナーには、アルバムを先に見せずに、先入観なしで、だまってまず曲を聴いてもらって」
◇◇◇
Oh! Lady Be Good Ella Fitzgerald Vol.3 Original 1945-1952 recording NAXOS JAZZ LEGENDS 8.120716 2003/6/2 Release

第28回 不滅のジャズ名曲-その28-アヴァロン(Avalon)
Murphy:「Djangoくん、このあいだの第25回で話題になった、ビール・バーのプランニングを担当しているデザイナーにさっそく、あのジャンゴのボックスセットを聴いてもらったところ、イメージにピッタリだといって、大変喜んでいたよ。お店のインテリアプランもほぼ出来上がり、あとは音楽の方のセレクト段階に入ったということだ。あ、それから、あと、ビールのセレクト![]()
がまだ不十分だと言っていたね。」
Django:「そりゃよかった。ジャンゴを気に入ってもらってよかった。」
M:「例の5枚組のアルバムなんだけど、実はそのデザイナーも以前にジャンゴのCDを買ったことがあったそうだよ。でも、録音が古くてあまり聴く気にならなかったって言っていた。でも、Djangoくんの推薦したそのアルバムの1枚目を聴いたとたんに、驚いたらしい。ボクも正直言ってびっくりした。1930年代のこんな古い時代の録音がここまで、いい音質で聴けるとは。それに演奏がすばらしかったね。」
D:「ボックス・セットの5枚組の1枚目は、ジャンゴがヴァイオリンのステファン・グラッペリと組んで、QHCF(フランス・ホットクラブ・五重奏団)を結成したときの、ファースト・レコーディングだから、その意気込みが傑作を生んだんだろうね。1934〜35年だからね。Murphyくんは、どの曲が気に入った。」
M:「全部だよ。しいてあげれば、アヴァロン(Avalon)かな。」
D:「ああ、あの曲のスイング力はすさまじいね。さすがMurphyくん、いい曲選ぶね。」
M:「アヴァロンって、以前に聞いたことあるような気がするんだけど。」
D:「そうだね。スイング時代によく演奏された名曲だよ。ベニー・グッドマンが大ヒットさせた曲だね。1920年に作曲された古い曲で、プッチーニのオペラ「トスカ」第3幕のアリアがベースになっていると言われている。ジャンゴの演奏は、いろんなアーティストの数ある演奏のなかでも、最も印象に残る名演だと思う。」
M:「ところで、そのデザイナーが、もうひとつDjangoくんに聞きたいっていってたんだけど。今のミュージシャンで、誰かそういった音楽をやっているグループがいるかどうか。」
D:「なるほど、ジャンゴ系のスイング・ジャズを今もやっているグループね。1つ紹介しようか? あまり、日本では、知られていないと思うけど、パール・ジャンゴ(Pearl Django)というグループ。グループの編成は、ジャンゴと同じ。いわばジャンゴの遺伝子を持ったグループということ。アルバム名は、ズバリ「アヴァロン(Avalon)」
M:「そうか、さっそく彼に伝えるよ。」
D:「Murphyくん、でもね、やっぱりオリジナルのジャンゴの演奏がなんといっても最高だね。いくら録音が古くても、その時代ならではの生きた音楽だし、その当時の最前線だったからね。グラッペリとの絶妙なコンビ、時代を先取りした新しさは、今聴いても新鮮だ。」
M:「わかった。あくまでジャンゴの当時の演奏があっての今だからね。」
D:「その上で、ジャンゴのDNAを持ったグループが、これからの時代、活躍してくれることは、ボクにとっては大変うれしいことだね。とくに、今の時代、ふたたび、あのジャンゴスタイルが求められていると思う。新しいグループは、ライブでその演奏に接することもできるし、彼らなりの新しい解釈も加味されているから、今後楽しみだね。」
M:「ところで、ジャンゴって、何度も聴きたくなるね。」
D:「そのとおり。毎日聴けば仕事の疲れも吹っ飛ぶし、からだもスイングし始めるよ。これ、”Django効果”というんだ。からだがスイングすると、いいアイデアも浮かぶし、発想が豊かになる。」
M:「おもしろいこというね。Django効果か。Djangoくんは、もうその効果がでてるの?」
D:「あたりまえだろう。ボクは、もともと名前からしてDjangoなんだから。」
◇◇◇
Avalon Pearl Django (Modern Hot Records) 2000/11/7リリース
 Neil Andersson(Guitar),
Neil Andersson(Guitar),
Michael Gray(Violin),
Rick Leppanen( Double Bass),
Greg Ruby(Guitar),
Dudley Hill(Guitar)
第27回 不滅のジャズ名曲-その27-ニューヨークの秋(Autumn in New York)
Django:「Murphyくん、久しぶりに今回は女性ヴォーカルを採り上げたいと思うんだ。ブロードウェイのミュージカルのヒットナンバーは、これまで多くのジャズ・シンガーに歌われてきたけど、そういったミュージカルの名曲ばかりを集めたアルバム。」
Murphy:「そのアルバムはDjangoくん、かなり気に入っているの?」
D:「そのとおり。「大都会のノスタルジーを歌った極めつけの名唱」というコピーが、アルバムの帯に書かれているとおり、聴いていて実に心地よい素敵なアルバムだね。」
M:「それで、誰が歌っているの?」
D:「白人女性歌手で、「ジョー・スタッフォード」という人。40、50年代に大活躍した人。伴奏は、ポール・ウェストン楽団。バックがストリングスの入ったオーケストラだから、ノスタルジックな映画を見ているようだ。このアルバムは、これまであまりジャズにふれていない人にも、おすすめだね。古きよき時代の映画が好きな人にピッタリだろうな。」
M:「どんな歌い方?」
D:「Murphyくん。一度聴くと絶対に気に入るよ。あまり黒人ぽい歌い方の人は苦手だといっていたね。ジョー・スタッフォードは、さらっとした歌い方。原曲に対し忠実に歌い上げる人。それとほとんどビブラートをかけずに、息の長いフレージングで歌うのが特徴。」
M:「そうか、あまり歌い方にくせがないんだね。」
D:「そのとおり。いわゆる”トランペット・ヴォイス”と呼ばれる歌唱法をマスターし、トロンボーン奏法からヒントを得たという、独自の管楽器に近づけた歌い方が特徴で、しかもさらっと歌いあげるところが魅力だね。」
M:「アルバム名は?」
D:「1曲目の「ニューヨークの秋(Autumn in New York)がアルバム・タイトルになっている。アルバムのなかで、やはりこの曲が一番いいね。」
M:「だれの作曲?」
D:「ヴァーノン・デューク。「パリの四月」を書いた人。この曲は、ジャズのスタンダード曲として多くのシンガーやプレーヤーが吹き込んでいる。演奏では、チャーリー・パーカーやソニー・スティット、チェット・ベイカーなど。シンガーでは、ビリー・ホリディやフランク・シナトラなど。」
M:「この一曲だけがいいんじゃない?」
D:「このアルバムに限っては、そんなことないね。確かにこの曲が突出しているかもしれないけれど、どれもいい曲ばかりだよ。他にジュローム・カーンの曲で「煙が目にしみる」、リチャード・ロジャーズのミュージカル南太平洋のなかのヒット・ナンバーで「魅惑の宵」などが入っている。」
===================================================
Autumn in New York(1934)
◆作詞・作曲:Vernon Duke
◆Key:F major
◆形式:A1 – B – A2 – C
◆主な収録アルバム:Charlie Parker with Strings (Verve)
◆推薦アルバム:Joe Stafford(vo) “Autumn in New York” (Capitol)
===================================================
ニューヨークの秋 ジョー・スタッフォード 1955年録音

Autumn in New YorkとStarring Jo Staffordの 2枚のアルバムのカップリング版
Autumn in New York/Starring Jo Stafford

第26回 不滅のジャズ名曲-その26-ボーイ・ミーツ・ゴーイ(グランド・スラム)(Boy Meets Goy (Grand Slam))
Murphy:「Djangoくん、前回のジャンゴのアルバム、ボクも初めて聴いたんだけど、とってもよかった。素晴らしくスイングしているね。それにヴァイオリンが加わって、とてもいい雰囲気だね。」
Django:「そうだろう。以前は録音が古いこともあって、聴きづらかったんだけど、ずいぶんクリアになったしね。ジャンゴのギターが生き生きと響くようになった。」
M:「そうだね。ところで、ジャンゴを聴いて、少しジャズギターに興味を持ったんだけど、まず何から聴けばいい?」
D:「Murphyくんは、アコースティック・ギターを演奏するんだろう。マーティンのギターについても詳しそうだし。ジャズギターはあまり聴いてなかったの?」
M:「うん。自分で演奏しようと思っても、あまりにもむずかしくてね。ちょっと敷居が高そうだし。」
D:「確かにジャズギターは、それなりのテクニックが必要なんだけど。聴いて楽しむ分には関係ないから、是非聴いてみたらどう?」
M:「うん。それで、まず誰から聴けばいい?」
D:「そうだな。Murphyくんはけっこう古いものが好きだから。それにあまりうるさくないものが好みだろう?」
M:「オールドファッションというか、レトロなものが好きだね。それと、やはりスイングしているもの。」
D:「そうか。この前、Murphyくん、戦前の古いハワイアンなんか聴いていたね。そのぐらい古くてもいいの?」
M:「その方がいいよ。あのハワイアン、Djangoくん覚えていたのか。」
D:「しっかり覚えているよ、あれよかったね。ところで、今回のアルバムなんだけど、ジャズギターで最高のものを選ぼうか?」
M:「いきなり? むずかしくない?」
D:「全然、そんなことないから安心して。それより、Murphyくんがジャズギターに興味を持ったんだから、この際中途半端なものはだめだと思ったんだ。それに、Murphyくん、アコースティックギターをやっているからね。」
M:「誰の演奏?」
D:「このアルバム、BGMで聴いてもいいと思うよ。いわゆるスイングジャズで1939年から40年ごろの演奏だから。レトロな味わいがあるよ。1曲3分前後だからすぐ終わるし。でも、ギターのパートが出てきたらいつか真剣に耳を傾けてくれる?」
M:「Djangoくん、また始まった。もったいぶるなよ。はやく言えよ。」
D:「わかった。伝説のジャズギタリスト、ビバップの元祖、チャーリー・クリスチャン。その彼が、ベニー・グッドマン六重奏団に加わっていた頃のアルバムで、「ザ・オリジナル・ギター・ヒーロー」というアルバム。そのなかに入っている、「ボーイ・ミーツ・ゴーイ(グランド・スラム) (Boy Meets Goy (Grand Slam))」という曲を是非聴いてくれる?」
M:「チャーリー・クリスチャンって、聞いたことあるなあ。確かギブソンのギターでチャーリー・クリスチャンモデルっていうのがあったと思うけど、その人?」
D:「そのとおり。そのギター、ギブソンのES-150っていうモデルだね。」
M:「どんな演奏なの。」
D:「このボーイ・ミーツ・ゴーイでみられる彼のアドリブソロは、フレーズがものすごくカッコいいんだ。非常にシンプルで、音に全く無駄がない。シンプルなアドリブ・フレーズで、一つの音を的確なところに落とし込むことがどれほどむずかしいものかは、多くのジャズギタリストが指摘しているが、彼はいとも容易くやってのけ、カッコいいフレーズを連発する。」
M:「へえ、そんなにシンプルなの?」
D:「そのとおり。すばらしいテクニックをもったジャズギタリストは、多く存在するが、彼ほどシンプルで生き生きとしたフレーズを奏でることのできるギタリストはいないね。それと一音一音が太くて明晰で、リズム感がすばらしい。かつてジム・ホールが、ボーイ・ミーツ・ゴーイでのチャーリー・クリスチャンのアドリブラインを自ら弾きながら、目を輝かせて、「素晴らしいフレーズだ。」と言っていた。「ボクはこのフレーズを弾きたくてギターを練習したんだ。こんなにカッコいい、フレーズを連発するチャーリーは本当に素晴らしいね。」って生き生きと語っていたんだ。」
M:「そうか、他のジャズギタリストにも影響を与えてるんだ。」
D:「そのとおり。実は先ほどのアルバムは、2002年に4枚組で発売された「チャーリー・クリスチャン/ザ・ジーニアス・オブ・ザ・エレクトリック・ギター」のダイジェスト版なんだけど、ボックスセットのライナーノートに、多くのギタリストからのチャーリーに対する絶賛の言葉が集められている。レス・ポール、ウエス・モンゴメリー、ジョージ・ベンソン、タル・ファーロウ、バーニー・ケッセル、B.B.キング、ラッセル・マローン、ジョン・スコフィールドなど、蒼々たるギタリストがこぞって絶賛している。実は、ボクも、この曲のアドリブフレーズを弾けるようになりたくて、ジャズギターを始めたんだ。いまでも何てカッコいいフレーズだなあって思うね。」
M:「そうだったのか。」
◇◇◇
ザ・オリジナル・ギター・ヒーロー ダイジェスト版 チャーリー・クリスチャン 1939〜1941年録音 Benny Goodman Sextet

ザ・ジーニアス・オブ・ザ・エレクトリック・ギター 完全版4枚組セット

アウトドア仕様、オリンパスμ770SW発売開始
アウトドアのために生まれたカメラOLYMPUS・μ770SWが3月2日発売された。昨年秋に発売されたμ725SWとの主な違いは、水中5mまでだったのが10mまで防水機能が強化されたこと、さらに堅牢性が増したこと、マイナス10℃の環境での動作を可能にしたこと、ハイパークリスタル液晶モニターの表面輝度アップならびにコントラスト比が20%向上したことなどがあげられる。μ725SWから短期間で新モデルのμ770SWを発売したことは、オリンパスのこのシリーズへの意気込みが感じられる。強化された性能をみると、どれもより本格的なアウトドアへの対応力を高めたものであり、決して表層的なマイナーチェンジでない点で好感が持てる。
実は、昨年11月からμ725SWを使用して以来、まだ3ヶ月した経過していないが、こんなに早くその上位機種が発売されるとは思ってもいなかった。μ725SWも継続して販売されるようだ。μ770SWとμ725SWは、仕様を見る限りレンズ構成は変わらない。8群10枚で、その内EDレンズ1枚、非球面レンズ3枚という非常に凝った構成である。このあたりのスペックで、オリンパスのレンズに対する妥協を許さないこだわりが感じれる。焦点距離は6.7mm〜20.1mmで、35mmカメラ換算では、38mm〜114mmの光学ズーム倍率3倍で、開放F値はF3.5(W〜F5.0(T)である。
これまでμ725SWを使用してきたなかで、一番実用的だと思った点は、レンズが飛び出さないことである。これは実際に使用してみないとなかなかその便利さが実感できないが、電源を入れて撮影状態に入っても、レンズがボディ内に格納されたままの状態で撮影でき、望遠側にズームしても飛び出さないという点が大きな特徴である。レンズがボディに格納されたまま撮影可能であるということは、最もアウトドアで役立つ機能だと使ってみてつくづく思った。いくら沈胴式のレンズを搭載しても、撮影モードでレンズが飛び出すと、レンズ部をどうしてもかばうようになり、ラフな使い方はできなくなってくる。その点μ725SWはレンズが飛び出さず、撮影時の軽快さを維持している。
レンズ表面の撥水コート処理も不可欠な機能である。雨にぬれたり、水の中につけると、必ずレンズに水滴が付着し、取り除かないと画像がぼけてしまうが、この処理によりレンズ表面にほとんど水滴が残らなくなった点は、小さな工夫であるが、実用上大変役にたつ点である。
レンズについては、現状35mm換算で広角側が38mmであるが、これがもう少し広角側にシフトしてくれればよいのだが。あとわずかであるが35mmになればさらに実用価値が高まると思う。カメラの写りについては、実用上全く問題ないレベルである。この種のアウトドア用カメラは、記録性が第一であり、「ちゃんときちっと」写ればよいと思っている。「ちゃんときちっと」ってどの程度かといえば、いざというときにA4サイズぐらいまで引き延ばしても十分鑑賞に耐えられる写りだと思っているが、すでにその程度の描写力は、この機種を含め500万画素以上のカメラなら十分合格点をつけられる機種も多いわけであり、とくにこの機種においても描写性能はなんら問題ないといえる。というより、ボディ内にレンズが格納されたまま飛び出さないという制約のなかで、新開発された屈曲型のレンズでありながら、従来型レンズと同等以上の描写性能を持っていることが特筆すべき点である。 一昔前までのデジカメは、画素数が増大しても、レンズ性能がついていけず、写りのよくない機種がかなり存在していた。特に歪曲収差については、いまでもいっこうに改善されてない機種も依然存在する。デジタル一眼レフにおいても、デジタル対応以前の旧モデルの廉価版ズームレンズを装着すると、とたんに描写性能が劣化するものが少なからず存在する。デジタルカメラにおいては、レンズ性能が非常に大切であることは言うまでもない。その点、オリンパスのデジカメは、画素数とレンズ性能との関係において、非常にバランスがよく、レンズについては決して妥協しないメーカーである。このことが、μ725SWにおいても実感できた。
一昔前までのデジカメは、画素数が増大しても、レンズ性能がついていけず、写りのよくない機種がかなり存在していた。特に歪曲収差については、いまでもいっこうに改善されてない機種も依然存在する。デジタル一眼レフにおいても、デジタル対応以前の旧モデルの廉価版ズームレンズを装着すると、とたんに描写性能が劣化するものが少なからず存在する。デジタルカメラにおいては、レンズ性能が非常に大切であることは言うまでもない。その点、オリンパスのデジカメは、画素数とレンズ性能との関係において、非常にバランスがよく、レンズについては決して妥協しないメーカーである。このことが、μ725SWにおいても実感できた。
振り返れば、オリンパスペンが開発されたとき、ハーフサイズなるが故に、レンズの重要性を認識し、高性能なレンズを搭載し、結果としてハーフサイズながら35mmフルサイズにも負けない描写力をもったことが、その後のペンシリーズの爆発的な人気に至ったわけである。 オリンパスペンシリーズは、いまだに大切に使っているが、このμ725SWを使っていると、どこかペンを使っているときのような気分になる。オリンパスペンを持って撮影にでかけると、いまでも肩の力が抜けてリラックスした気分になる。小型軽量のボディでレンズも飛び出さないし、ハーフサイズ独特の軽快感が楽しい。撮影する視線も変わってくる。いままで見逃していた光景やモノに注目するようになる。これを自分では「PEN効果」と勝手に思っているが、そういった気軽さが、μ725SWを使っているときも感じられる。しかも、ペンと違って、今度は、防水だ。堅牢性は高い、その上1ギガのカードを入れれば数百枚写せる。レンズも、ペンの思想と同様、こだわりを持っている。いざというときは、大きく引き延ばせる。あとは、次期モデルで、なんとか広角側が35mm(35mm換算)にならないかと願っている。
オリンパスペンシリーズは、いまだに大切に使っているが、このμ725SWを使っていると、どこかペンを使っているときのような気分になる。オリンパスペンを持って撮影にでかけると、いまでも肩の力が抜けてリラックスした気分になる。小型軽量のボディでレンズも飛び出さないし、ハーフサイズ独特の軽快感が楽しい。撮影する視線も変わってくる。いままで見逃していた光景やモノに注目するようになる。これを自分では「PEN効果」と勝手に思っているが、そういった気軽さが、μ725SWを使っているときも感じられる。しかも、ペンと違って、今度は、防水だ。堅牢性は高い、その上1ギガのカードを入れれば数百枚写せる。レンズも、ペンの思想と同様、こだわりを持っている。いざというときは、大きく引き延ばせる。あとは、次期モデルで、なんとか広角側が35mm(35mm換算)にならないかと願っている。
◇◇◇
撮影データ:( )内は35mm換算の焦点距離
左上:μ725SW 6.7mm(38mm) 1/20秒 F3.5 ISO200
右下:μ725SW 6.7mm(38mm) 1/500秒 F6.3 ISO80