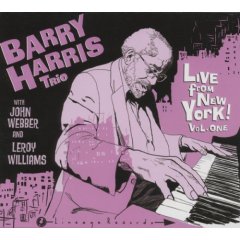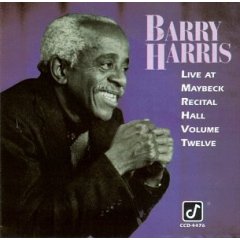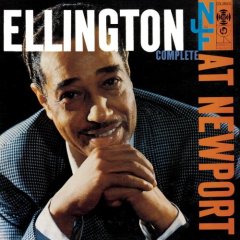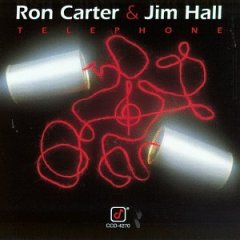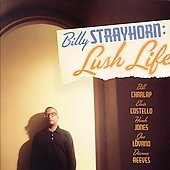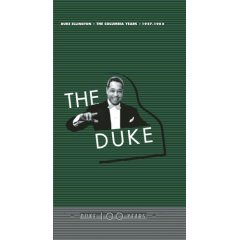デューク・エリントン。偉大な作曲家、ピアニスト、アレンジャー、楽団経営者、音楽プロデューサー、その肩書きは一言では言い表せない。自分が今、最も関心の高い音楽家であることは間違いない。
いい音楽を聴くといつまでも心に残る。ジャズもそうだ。でも、案外ジャズは普段生活の中で、いつまでもそのサウンドが頭の中で鳴り響くことは少ない。直接その音楽に接しているときだけ、ジャズを味わい、終わるとサウンドそのものはすぐに消えていく。言ってみればジャズは、瞬間の音楽であり、聴き手は演奏者のアドリブをリアルに追いかけていくのが醍醐味だ。聴いた後いつまでもそのサウンドが思い出され心に響くことは少ない。
しかし例外もある。二人の音楽家。一人はチャーリー・パーカー。何回も聴いているとアドリブフレーズの断片が記憶に残る。でも、パーカーは風のようだ。スーっと消えていく。いま掴んだと思ったら手の中には空気だけが残る。だからまた聴こうとする。何回聴いても聴きあきない。形になって残らないから聴くたびに新鮮だ。
もう一人は、デューク・エリントン。パーカーと違って、聴き終わった後いつまでも残る。頭のなかでそのサウンドが鳴り響く。オーケストラのサウンドの断片が思い出される。例えば、1957年にエリントンがシェイクスピアを読んで深く感動し、そのインスピレーションから書き上げた、Such Sweet Thunderという曲。これを聴いた後、いつまでも頭の中で鳴り響いた。ある特定の楽器が思い出されるのではなく、オーケストラのサウンド全体がいつも思い出される。
エリントンの音楽は、メロディがどうの、ハーモニーがどうの、リズムがどうのというように、分解してその特質が語られてきた。そうしないと説明がつかないからだ。エリントンのような複雑な音楽は、その特異性を指摘する上では、さまざまなアプローチから分析しなければ実態に迫ることはむずかしい。そのことはよくわかっている。自分でもいつかそういった理論を調べてみたい。でも、今はこの不思議なエリントン音楽をひたすら味わい続けたいと思う。エリントンの音楽は、ずいぶん複雑で不思議な音楽に聴こえるが、自分ではきわめて具体的でわかりやすい音楽だと思っている。もちろん聴き始めた頃は、さっぱりわからなかった。でも、聴き続けると、これほど魅力的な音楽は、そうは世の中にないと思うようになった。いやこれはクラシックの分野を含めてもである。つまり、20世紀のあらゆる音楽のなかでも、エリントン音楽は最も魅力的な音楽の一つであると思っている。しかもその音楽は、きわめて絵画的である。エリントン音楽の持つ特異なサウンド・テクスチェアは、キャンバスに描かれた絶妙な色彩を味わうときのイメージに近い。だから、エリントンの音楽は、絵画のようにいつもそのサウンドの断片が思い出される。