Murphy:「4/20の大阪ブルーノートでのジム・ホールとロン・カーターのデュオは本当に素晴らしかったね。Djangoくんに誘われて行ったんだけど正直言って驚いたよ。ジャズの演奏というのは大音量だと思っていたんだけど、意外に小さくて、アンプを通しているにもかかわらず生音のようなピュアな音だった。ギターとベースのサウンド・クォリティはさすがだね。耳を澄ませて思わず聴き入ってしまった。それと、ジムホールがあの年齢で、エフェクターを通して様々なサウンド作りをするからびっくりした。本当に行ってよかったよ。次の日も、余韻が残っていたし、もう一度聴いてみたくなった。」
Django:「いい音楽は、聴いた後の余韻がいつまでも持続する。Murphyくんの言うようにもう一度聴いてみたくなるね。ロン・カーターはライブで、PAには最新の注意を払っているし、ベースの生音にできるだけ忠実な再生を心がけている。ジム・ホールも同様で、二人とも究極のエレクトリック・アコースティックサウンドを目指している。」
M:「よくアマチュアのジャズライブを聴きにいくと、これなら家のオーディオでCDを聴く方が余程よいサウンドだと思うことがある。音量が大きすぎてうるさくて長時間聴き続けると疲れてくることもあった。PAは大切だね。」
D:「その通り。現在第一線で活躍するジャズプレーヤーのライブ演奏は、概して思ったほど大音量ではない。特にロン・カーターなんかは、サウンドクォリティを最優先するし、音量もかなりセーブしている。ジム・ホールも80〜90年代に較べ、最近はますます音量を小さくする傾向にある。MJQなんかは、昔からいつも適正な音量で定評があったし、室内楽的サウンドクォリティを追求していた。」
M:「ジム・ホールは生で初めて聴いたんだけど、今回使っていた楽器はなに?」
D:「ギターはSADOWSKY(サドウスキー)のジムホール・モデル。アンプはポリトーン。」
M:「ジム・ホールが最初ステージに現れたとき、かなりのお年だと思ったけど、何歳ぐらいなの?」
D:「ジム・ホールは1930年12月4日生まれで76歳。一方のロンカーターは、1937年5月4日生まれだからもうすぐ70歳になる。」
M:「でも、演奏はいつまでも若々しいね。」
D:「そのとおり。ひとたび演奏が始まると、二人とも驚くほどクリエイティブな演奏を展開する。当日の最初の曲は、マイ・ファニー・ヴァレンタイン、2曲目はジム・ホールのオリジナル・ブルース・ナンバーでケアフル、3曲目は確かpeaceというオリジナル曲、4曲目は、オール・ザ・シングス・ユー・アー、ラストは、ソニー・ロリンズのセント・トーマス、そしてアンコールはミルト・ジャクソンのバグズ・グルーブだった。ところで、2曲目のケアフルという曲は、通常ブルースは12小節なんだけど、16小節だから注意しなければいけない、という意味でジム・ホール自らが、ケアフルと名付けたらしい。」
M:「Djangoくんが、ジム・ホールを聴くなら出来るだけステージに近い席で聴く方がいいと言っていたけど、最前列で聴いてよかったな。アンプを通したり生音のままで伴奏したり、ジム・ホールがあれほど音色を変えるとは思っていなかったので驚いた。」
D:「ジム・ホールも80年代の頃はライブでもっと大きな音量だったけど、先ほども言ったように最近はかなり小さくなった。そのことによって、聴衆は耳を澄ませ、積極的に聴こうとするようになるんだ。その分以前にも増して、多彩な音色を追求するようになった。」
M:「ところでDjangoくんは、いつ頃からジム・ホールが好きになったの?」
D:「70年代からだね。それ以前はあまり知らなかった。60年代初めのソニー・ロリンズのバンドに参加していた頃の演奏は、あとで知った。70年代に入り、マイルスが電化サウンドにシフトし、多くのプレーヤーがフュージョン路線へとシフトし始めた頃から、最新録音盤は徐々に購入を見合わすようになったんだけど、ジム・ホールだけは例外だった。彼の演奏は一番肌に合うと言うか、体質的に最も受け入れやすかったので、よく彼の演奏を聴いていた。もし、ジム・ホールがいなかったら、途中でジャズを聴かなくなっていたかもしれない。
70年代の後半から、カリフォルニアでカール・E・ジェファーソンがコンコード・レーベルを主宰し、次々と往年のスインギーなジャズプレーヤーを起用し録音するようになった。特に、ハーブ・エリス、カル・コリンズ、ジョニー・スミス、ジョージ・ヴァン・エプス、ケニー・バレルなどの名ギタリストを起用して数々の優れたギターアルバムを制作した。これは画期的だったね。フュージョン一色の時代に、往年のフォービート・ジャズ復活を復活させた功績は多大だ。当時このコンコードレーベルの輸入LPを好んで購入するようになった。コンコードレーベルは、ジム・ホールの新録音も開始し、ジム・ホールとロン・カーターのデュオアルバムLive at Village Westが82年にリリースされた。続いて84年にふたたびリリース。これが、再会セッションといわれるテレフォン(Telephone)というタイトルのアルバム。その中に収録されているアローン・トゥゲザー(Alone Together)は、70年代にリリースされた二人のデュオアルバムのタイトルにもなった曲。」
M:「それにしても、二人のデュオはもう一度聴きたくなるね。」
D:「素晴らしいライブに触れたときはいつもそうだよ。」
◇◇◇
Ron Carter and Jim Hall / テレフォン(Telephone)
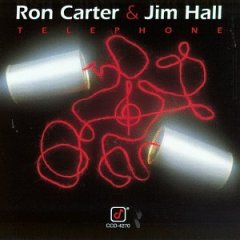
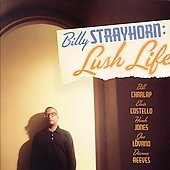

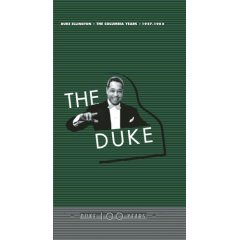

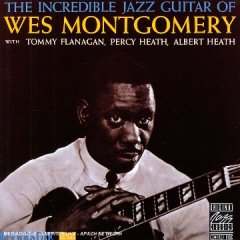



 残念ながら、彼は1955年に亡くなり短命に終わっている。だから、作品の数は少なく、それほど知名度も高くなかった。しかしそのアドリブは一度聴くと忘れられないほどの魅力を持ち、聴き手を引きつける。フレーズが自然でなめらかだ。しかも、フレーズの間(ま)が絶妙で、全く抵抗なく聴き続けられる。こちらの耳が、積極的にアドリブ展開を聴き逃さないように追いかけるようになる。ソニー・ロリンズ出現以前では、最もよく歌うモダンテナーだとも言われている。チェースのアルバムでは大和明さんがライナーノートを担当。岡崎正通さんとの共著モダン・ジャズ決定版で、氏は以下のようにワーデル・グレイを絶賛している。(Djangoより)
残念ながら、彼は1955年に亡くなり短命に終わっている。だから、作品の数は少なく、それほど知名度も高くなかった。しかしそのアドリブは一度聴くと忘れられないほどの魅力を持ち、聴き手を引きつける。フレーズが自然でなめらかだ。しかも、フレーズの間(ま)が絶妙で、全く抵抗なく聴き続けられる。こちらの耳が、積極的にアドリブ展開を聴き逃さないように追いかけるようになる。ソニー・ロリンズ出現以前では、最もよく歌うモダンテナーだとも言われている。チェースのアルバムでは大和明さんがライナーノートを担当。岡崎正通さんとの共著モダン・ジャズ決定版で、氏は以下のようにワーデル・グレイを絶賛している。(Djangoより)
